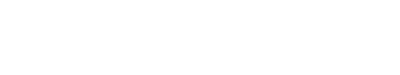『モノ・マガジン』という発明【新保信長】新連載「体験的雑誌クロニクル」7冊目
新保信長「体験的雑誌クロニクル」7冊目
『ギア・マガジン』はタイトルからして似ているし、誌面の構成やデザインも似通っていた。『グッズプレス』はサブタイトルが「世界のモノ情報」で「モノ」に「MONO」と(『モノ・マガジン』の略称を思わせる)ルビを振り、「日本一のモノ情報量で創刊」と謳っているあたりに『モノ・マガジン』への対抗心がうかがわれる。『ビギン』は、のちに『レオン』を創刊する岸田“ちょいワル”一郎氏が編集長を務めただけあって、物欲と性欲が拮抗している。創刊号の特集は「いますぐ『欲しい』『したい』ハイパーインデックス108」と題して108の煩悩をピックアップ。その中には「女のコが多いツアーに参加したい」「リゾートで確実に女のコをモノにしたい」なんてのもあった。2号目の特集は「ヤルぞ!クリスマス」。『モノ・マガジン』より『ポパイ』や『ホットドッグ・プレス』をめざしていたのかもしれない。

一方、『モノ・マガジン』の創刊は1982年。「欲しいものを発見できるスーパーグッズマガジン」というのが当初のキャッチコピーだった。創刊号の特集は「NASAスピンオフ」と、いきなりマニアック。が、それが同誌の特色でもあった。ミリタリーやアウトドア、ヘビーデューティ系グッズを積極的に扱う。ハイテクメカも大好きで、2号目の特集「アメリカ日用雑貨」のようにアメリカ文化への憧れも強い(そのへんはおそらくベトナム戦争の従軍カメラマンだったという噂の社長の趣味だろう)。
もうひとつの特色は「モノ・メールオーダー」というコーナーを設け、おすすめの品を通販で買えるようにした点だ。のちに「モノ・ショップ」という実店舗も展開。1988年の時点では銀座、上野、静岡、名古屋の4店舗を抱えていた。今もウェブショップがあるが、誌面でプッシュした品を自社の通販や店舗で販売するという一石二鳥のアイデアには感心した。その手法でMA–1などのフライトジャケットを流行らせたのも(映画『トップガン』の影響はあったにせよ)『モノ・マガジン』である。
同誌が初めてフライトジャケットの大特集を組んだのは1987年12月2日号。その前号で創刊以来の平綴じ・月刊から中綴じ・月2回刊(「情報号」「特集号」と区別しているが違いはよくわからない)にリニューアルしており、フライトジャケット人気も相まって一気に雑誌としてのメジャー感が出た。
真偽のほどは定かでないが、編集部の先輩に聞いて「なるほど」と思ったのは『モノ・マガジン』創刊にまつわる裏話だ。出版社には、いろんなメーカーから新製品のプレスリリースが大量に届く。その情報はもちろん無料である。じゃあ、それで雑誌を作ってしまえばいいじゃないか――というのがそもそもの発想だったという。
新製品を紹介する記事はそれまでの雑誌でもあったし、カタログ的雑誌の源流には伝説のムック『Made in U.S.A. catalog』(読売新聞社/1975年)の存在があるが、新製品情報“だけ”で雑誌を作るというのは画期的だった。それはひとつの発明と言っていいだろう。
その象徴が「ホットライン」という情報ページだ。「乗り物」「家電製品」「オーディオ&ビデオ」「光学製品」「食品」「衣料」「家庭雑貨」「インテリア&家具」「ホビー」「楽器」など16ジャンルの新製品をリリースの情報と広報写真で紹介する。創刊号では扉含めて59ページで、実に全体の約4割。88年当時でも33ページが割かれていた。担当者にとっては面倒くさく退屈なページだが、コスパは非常にいい(現在の誌面には存在せず)。

とはいえ、さすがにそれだけでは雑誌は成立しない。ただ新製品を紹介するだけでなく、ブランドヒストリーや開発秘話などのウンチク、著名人のエッセイ、インタビューなどで読者の興味を引く。特集自体の切り口も「小金持ちの小利口家電」(1989年3月2日号)、「次に買う時計」(同4月2日号)など、ひねりを利かす。カメラ特集(1990年3月16日号)では「人間活劇、まる撮り写真機」と題して、安珠、一色一成、沢渡朔、立木義浩、林忠彦、リウミセキといった有名写真家による撮り下ろしセルフポートレートを掲載。今見ると、いや、当時としてもめちゃ贅沢な企画である。